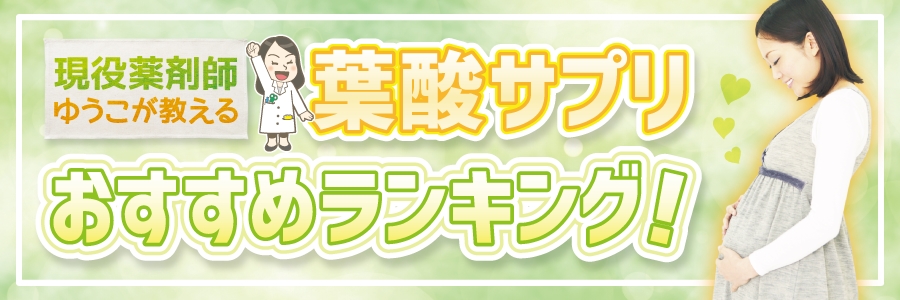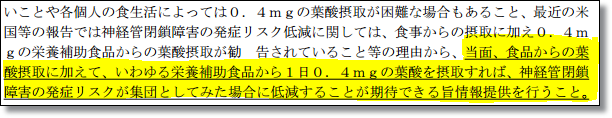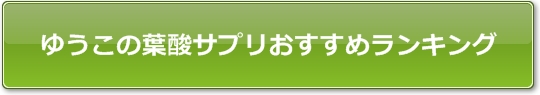厚生労働省が葉酸摂取を推奨している理由をやさしくまとめました!

 下記クリックで詳細ページに飛びます
下記クリックで詳細ページに飛びます
【目次】
厚生労働省はなぜ葉酸摂取を推奨しているの?
厚生労働省が、葉酸を推奨しているのは、先天性異常のリスク(神経管閉鎖障害による二分脊椎や無脳症)を減らす効果、それにともなう死産や流産の予防のためになります。
厚生労働省はなぜ葉酸摂取で栄養補助食品を推奨しているの?
栄養補助食品とは、食事で充分に摂れない栄養素を補う目的で、栄養素がカプセル、錠剤、粉末個包装紙、液状アンプル、液体型容器のかたちで濃縮されているものになります。
厚生労働省は、栄養補助食品から1日400μgの葉酸を摂取すれば神経管閉鎖障害の発症リスクが減ることを期待できる通知を出しています。

| 葉酸の種類 | 葉酸の特徴 |
|---|---|
|
モノグルタミン酸型葉酸 |
|
|
ポリグルタミン酸型葉酸 |
|
| 女性の年齢 | 葉酸の食事摂取基準(μg/日)の推奨量 |
|---|---|
| 18歳〜49歳 | 240μg(食事性葉酸) |
参考:日本人の食事摂取基準(2015 年版)の概要 平成26年国民健康・栄養調査結果の概要

栄養補助食品のモノグルタミン酸型葉酸が、生体内利用効率も高く厚生労働省から推奨されています。
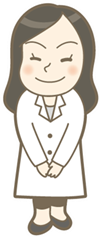
また、厚生労働省は、栄養補助食品で葉酸サプリと指定はしていません。ですが、確かにモノグルタミン型葉酸を400μgかつ他の栄養素も同時に摂れる葉酸サプリをおすすめしたいと考えます。

厚生労働省は葉酸をいつまで推奨しているの?どのくらいの摂取量を推奨しているの?
期間 |
推奨量(18〜49歳女性1日推奨量240μgに付加して) |
|---|---|
妊活中 |
+400(μg/日)モノグルタミン酸型の葉酸 |
妊娠1ケ月以上前〜妊娠3ケ月 |
+400(μg/日)モノグルタミン酸型の葉酸 |
妊娠中期〜妊娠後期 |
+240(μg/日)食事性葉酸(ポリグルタミン酸の葉酸)、モノグルタミン酸型の葉酸でも可 |
授乳期 |
+100(μg/日)食事性葉酸(ポリグルタミン酸の葉酸)、モノグルタミン酸型の葉酸でも可 |
葉酸が不足するとどうなるの?

葉酸が不足すると、動脈硬化の危険因子となるホモシステインをアミノ酸のメチオニンにする代謝が進まなくなり、ホモシステインが増えると血管内で活性酸素を作り動脈硬化になりやすくなります。
ホモシステインは、アミノ酸の一つであり、その代謝過程で、葉酸、ビタミンB6、ビタミンB12が関わっています。葉酸、ビタミンB6、ビタミンB12は、ビタミンB群として働き血中ホモシステインを減らします。
そして、適度な運動も、ホモシステインを減らすために効果的です。
その他、葉酸が不足し血を造る機能が、弱まると巨赤芽球性貧血、神経障害、腸機能障害が起こります。
厚生労働省は葉酸の過剰摂取量はどのくらいと決めてるの?
葉酸の耐容上限量(モノグルタミン酸型葉酸で算出)は、18〜29歳女性で900μg、30〜49歳女性で1000μgとなっています。
葉酸を過剰摂取するとどうなるの?

葉酸(モノグルタミン酸型葉酸)を上限量摂ると、発熱・蕁麻疹・紅い皮疹・かゆみ・呼吸障害などの葉酸過敏症を起こすことがあります。
葉酸は、ビタミンB12と働いて、赤血球の生産を助ける造血ビタミンと言われています。
赤血球は、骨髄でつくられている血液の主な成分です。全身に酸素を運び、いらない二酸化炭素を運び出します。葉酸を過剰摂取すると、ビタミンB12が足りなくなります。
ビタミンB12が不足すると赤血球の生産が減り、全身に必要なだけの酸素がなくなり、貧血の状態になります。
葉酸の影響がなく、ビタミンB12のみの不足では、末梢神経障害による痺れなどがあります。症状の違いもあるのですが、ビタミンB12欠乏症の診断を難しくします。
また、亜鉛と結合して一体になってしまい小腸からの亜鉛の吸収を抑制する可能性もあります。
オーストラリア、ニュージーランドでは、モノグルタミン酸型葉酸1000μg以下の摂取であれば、ビタミンB12欠乏症が起こりにくいことを伝えています。
葉酸サプリでは、ビタミンB12も同時に摂れることも大切なポイントになります。
妊娠後期(30−34週)に1000μgの葉酸(モノグルタミン酸型葉酸)のサプリを摂っていた場合、摂っていなかった場合と比較すると、小児が3.5歳の時に喘息になるリスクが1.26倍高かったという報告があります。
報告引用元:American Journal of Epidemiology Advance Access published October 30, 2009「Effect of Supplemental Folic Acid in Pregnancy on Childhood Asthma: A Prospective Birth Cohort Study」
信頼できる健康食品情報源(公的機関等)
- 国内の健康食品に関連する情報サイト
| 組織等の名称 | アドレス | 主な提供内容 厚生労働省 |
|---|---|---|
| 厚生労働省 | http://www.mhlw.go.jp/ seisakunitsuite/bunya/kenkou_ iryou/shokuhin/index.html | 食品の安全性確保に関する情報 |
| 内閣府食品安全委員会 | http://www.fsc.go.jp/ | 食品の安全性評価に関する情報 |
| 消費者庁 | http://www.caa.go.jp/foods/ index.html | 食品の表示に関する情報(特定保健用食品、栄養機能食品、特別用途食品など) |
| 国立医薬品食品衛生研究所(食品の安全性に関する情報) | http://www.nihs.go.jp/hse/food‐info/index.html | 食品の安全性に関する国内外の情報 |
| (独)国立健康・栄養研究所(「健康食品」の安全性・有効性情報) | http://hfnet.nih.go.jp/ | 健康食品に関する基礎的情報、各成分に関する有効性や安全性の論文情報、有害情報など |
| (独)国民生活センター | http://www.kokusen.go.jp/ | 健康食品に関する個別製品の検査結果など |
| 東京都(健康食品ナビ) | http://www.fukushihoken.metro. tokyo.jp/anzen/supply/index.html | 健康食品に関する情報 |
| (財)日本健康・栄養食品協会 )載。 | http://www.jhnfa.org/ | 製品の自主規格や業界として必要な情報など |
| 日本医師会(健康食品のすべて―ナチュラルメディシン・データベース | http://www.med.or.jp/ (メンバーズルーム(日本医師会員向け HP)よりリンク) | 健康食品の有効性、安全性、医薬品との相互作用(飲み合わせ)の解説など。症例も掲 |